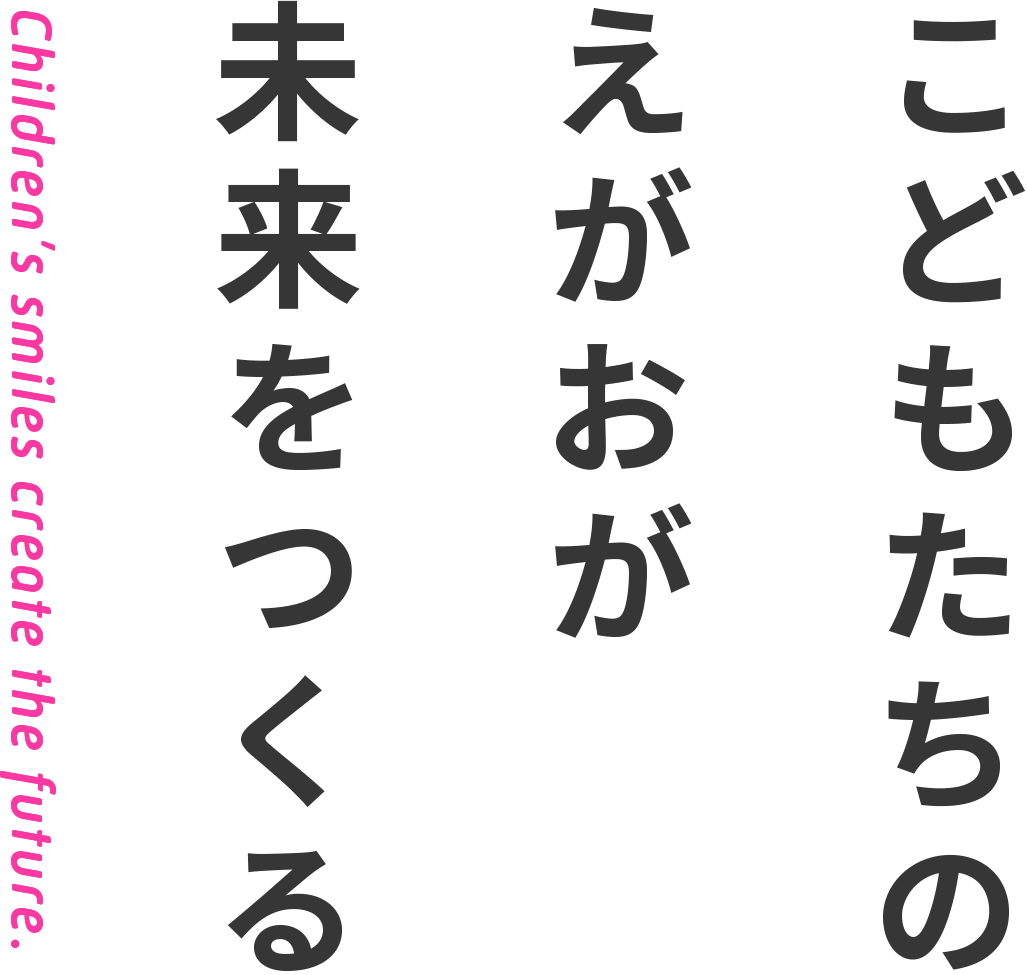
だれかが わたしを知っている。
だれかが わたしに元気をくれる。
だれかが そっと⼿を差し伸べてくれる。
おたがいに⽀え合って⽣きていく。
そんな社会のなかで ⼦ども達を育てたい。
性別も年齢も 障害があるとかないとか。
⼦どもが笑うと みんな笑う。
そう、だから⼦どもを笑顔にすることから始めよう
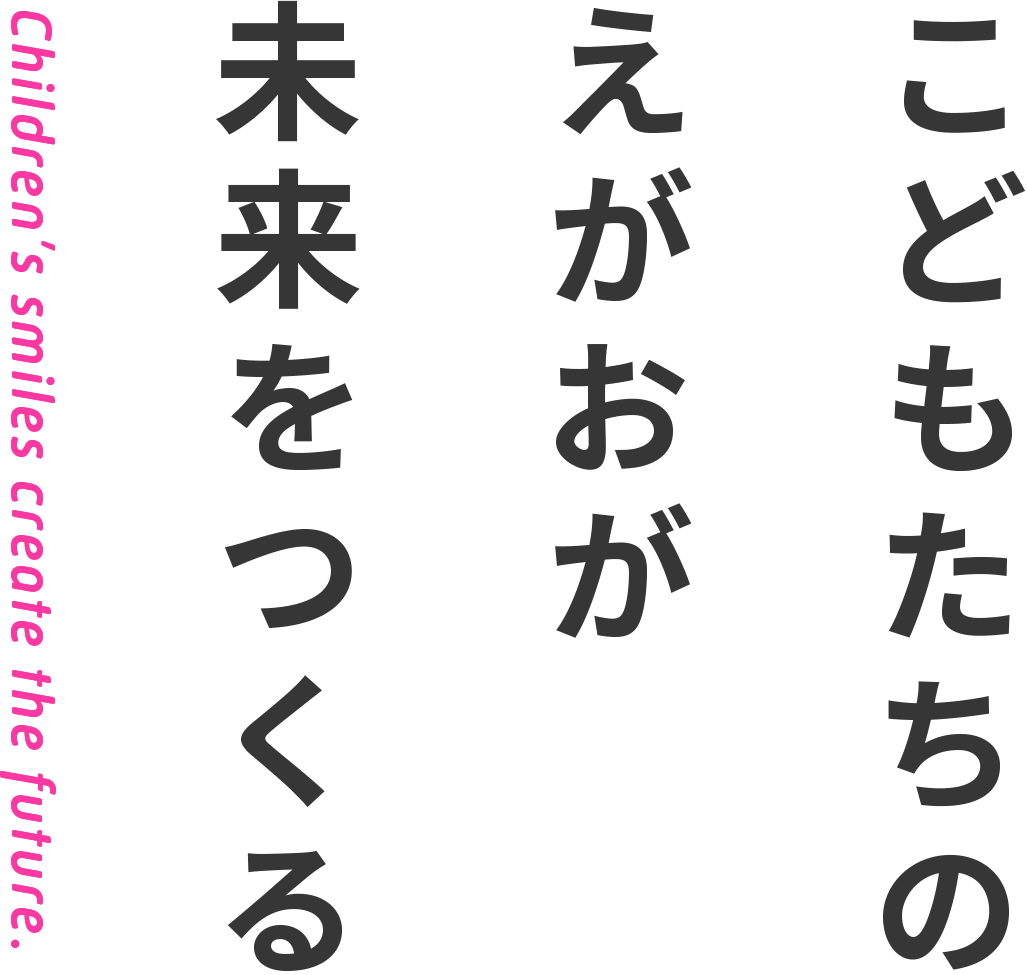
だれかが わたしを知っている。
だれかが わたしに元気をくれる。
だれかが そっと⼿を差し伸べてくれる。
おたがいに⽀え合って⽣きていく。
そんな社会のなかで ⼦ども達を育てたい。
性別も年齢も 障害があるとかないとか。
⼦どもが笑うと みんな笑う。
そう、だから⼦どもを笑顔にすることから始めよう



